日本IVR学会広報渉外委員会企画 日本産科婦人科学会・日本IVR学会理事長対談
「重要性を増す産婦人科医とIVR医の連携
産婦人科医の理解とIVR医の増員・認知拡大の取り組みの現状」
――日本産科婦人科学会と日本IVR学会の両理事長による対談は非常に貴重な機会と伺っています。今日は三つのテーマについて、現状やご意見を頂戴できればと思っております。一つ目は「産科危機的出血」について、二つ目は「子宮筋腫に対するUAE」について、そして三つ目は「婦人科悪性腫瘍」についてです。

左:木村正先生 右:山門亨一郎先生
本題の前に、先生方が直接お話をされるのは初めてということですので、先生方のこれまでの両科での経験や思い出を伺いたいと思います。
山門:私がこれまでお会いしてきた婦人科の先生は、ほとんどみなさん優しい先生でしたね。ただその優しさに目が行きがちですが、やはり外科医なんです。一緒に仕事しているとき、治療がうまくいくと一緒に喜んでくれて「やっぱり外科やな」と思っていましたね。しかも非常に義理堅く信頼関係ができやすいと、いつも頼もしく思っています。
――よく産婦人科の先生方はとても優しく、患者さんにとって相談もしやすいといわれていますね。
山門:本当に話を聞くのが上手な先生が多いですね。その分外来が長くなりやすいともいわれますが、これも科の特徴かもしれませんね。
――木村先生は長年産婦人科でご活躍されてきましたが、IVRの先生との思い出があれば教えてください。
木村:大阪大学は、日本でも比較的早くIVRでいろんな取り組みを始めた大学だと思います。正直、動脈塞栓術について、最初は「動脈を詰めていいのだろうか」と不安もありました。ただ2000年頃から、お産の後に強烈な出血をする産科危機的出血が増えてきたと感じており、その対処法として子宮動脈の塞栓術は非常に有効な方法でした。それまでは子宮から強烈に出血した場合は、子宮を摘出するしかありませんでした。ですがIVRにより動脈を詰めることで出血を制御することができるようになりました。
大阪大学は救命救急センターがあり輸血のストックがたくさんあるので、産科危機的出血の患者さんが搬送されてくることが多いのです。IVRの先生方には、本当にたくさんの患者さんを助けていただきました。子宮を残せたと喜んだ方も少なくありません。
ただこういったことは時間を選ばないので、夜中の1時や2時に「先生来てください」と呼び出しをかけることもあるのですが、IVRの先生方はいつも快く来てくださるので本当に感謝しています。大阪大学では以前はお一人の先生がほとんどのケースを対応していらっしゃいましたが、それがだんだんとチームになっていったことから見ても、IVRが着実に歩みを進めていることを感じますね。
――両科の先生が現場で信頼関係を築いてこられたのですね。ただ一方でIVRは体への負担が少なく様々な分野での活用できるにもかかわらず、一般の方への認知があまり広がっていない印象があります。なぜでしょうか。
山門:そこは大きな問題だと思っています。以前、日本専門医機構という認定機関から「『IVR』という名称がわかりにくい」「専門医名をもう少しわかりやすくしてはどうか」というご意見をいただきました。そこで学会の名前は「IVR学会」のままですが、専門医名は「放射線カテーテル治療専門医」とし、専門医機構からサブスペシャリティのお墨付きをいただきました。
IVRという名前はドクターには広まってきていますが、一般の人にはまだなかなか広まっていません。そこで今、学会の広報渉外担当を中心に啓発活動に力を入れているところです。
――山門先生は30年以上前に「これからはIVRだよ」という話を聞き、IVR医を目指したそうですね。この30年でかなり進んできたという実感はありますか。
山門:血管塞栓術は肝臓がんから始まった歴史があるのですが、1990年頃は肝臓がんに対する塞栓術の5年生存率は3%しかありませんでした。それが塞栓術の進歩とラジオ波焼灼療法などいろんな治療法が出てきたことで、2020年には70%ぐらいになりました。まさしく隔世の感があります。日進月歩ですね。
木村:医療もそうですし、患者さん側の意識もずいぶん変わってきましたね。昔は「何が何でも手術」という医療者が多かったし、患者さんも手術を希望する傾向がありました。それが生活の質(QOL)をどのように保つのかを考えるようになるなど、医療を受ける目的自体が変わってきています。また妊娠出産の現場では、女性が子どもを生む年齢が上がり社会の変化と共に対応する医療も変わってきていると感じます。
――産科婦人科の方にテーマを進めていきたいと思います。一つ目のテーマは「産科危機的出血」です。「産科危機的出血への対応指針2022」において、初めてIVRに関する内容が記載され、日本IVR学会という名前も使われました。背景を教えてください。
木村:日本は少子化の時代においても、まだ2000カ所ほど分娩をする場所があるのですが、これは外国の主要国の何十倍で、非常に多いのです。たとえば大阪の場合、880万人の人口に対して分娩施設は150カ所ほどあります。スウェーデンが900万人と、大阪と同じくらいの人口で、面積は大阪府に比べものにならないくらい広いのですが分娩施設は7カ所ほどです。妊婦さんはそこに集まって出産するのです。それらの施設にはさまざまな設備が整っているのですが、日本は小規模施設が多く、何でもあるという状況はつくれていません。ですから何かあったら、患者さんを大きな施設に搬送します。そこで今回の改定では、受け入れ側の施設がIVRを含めて大体のことはできるようにしておきましょう、という内容を盛り込みました。IVRをしていただける先生方が増え、IVRを行う施設が増えたことも一つの背景だと思います。
体中の血液が抜けるような出血への対応は、あちこちの病院で対処しない方がいいと思っています。大阪の場合は産科危機的出血を受け入れる病院が9カ所あり、今度10カ所になりますが、ほぼ全てのエリアから30分以内でいずれかにたどりつけるようにしています。救命センターの初料室で治療が始まり、我々産婦人科医がそこに行き、IVRの先生も必要であればそこへ来ていただきます。非常に効率的に動けるシステムです。
私はよく小さい施設で大量の出血が起こったら「そこで頑張らずに、搬送してください」とお願いしています。小さい施設で粘ると、どうしてもいろんなことが後手に回って条件がどんどん悪くなります。そこで時間を浪費するのであれば、すみやかに搬送するのがいいと思います。
山門:非常に共感するところがありますね。やはり産科の大量出血は一気にDICになり、どんどん状態が悪くなっていきます。30分違うだけでもかなり患者さんの状態が変わってきます。先ほどIVRの広報・啓発が必要だという話をしましたが、対応指針にIVRという名前を入れていただいたことで産婦人科の先生方が「こういう治療法があるのか」と知るきっかけになり、IVRに向けて動く一歩が早くなると期待しています。
大阪は木村先生のようにきちんと体制整備をする人がいて、IVRのドクターも結構多いのですが、各地のIVR医の状況を調べると東北地方などは非常に少ないのです。そういうところにもIVR医を増やして24時間駆けつけられるようにするためには、それだけの人数が必要です。IVR専門医を増やしていくことが、我々の一つの使命だと思っています。
僕が理事長になった2020年は2700人ほどのドクターがIVR学会に参加してくれていましたが、2023年4月で3000人を超えると思います。また日本専門医機構のサブスペシャリティにも認定されましたので、もっとIVR医を増やし、産科危機的出血などにどんどん対応できるようにしていきたいと考えています。また、産婦人科の教科書にもIVR治療を掲載し存在を知ってもらうなど、今後も協力して進めていただければと思っています。
木村:IVRでは、女性の先生の割合はどの程度でしょうか?
山門:10%ほどと低いですね。ダイバーシティ&インクルージョンの部会を作り、一所懸命リクルートをしているところです。
木村:医学部の入学者に占める女性比率が3割を超えるような時代になり、いろんな分野でますます女性の先生に活躍していただく必要があります。ただ女性で、特に家庭をお持ちの方、お子さんをお持ちの方にとって、夜中の突然の呼び出しは一番つらいと聞きます。そういった方々が活躍していただくためにも、あちこちの施設にIVRの先生が分散するのではなく、ある程度設備が整った施設に集約できる方が、安定して仕事ができて先生方の生活の質も技術も高まると考えています。
山門:木村先生のお考えには大賛成ですね。
木村:産科危機的出血でIVRを選択することには、低侵襲なので次の妊娠の可能性を残すという目的もあります。時々永久塞栓物質を使ったというレポートを目にしますが、産科側が出血を一刻も早く止めたいという気持ちでリクエストしてしまうケースもあるのでしょうが、次の妊娠のことを考えるとその選択はそぐわないと感じます。このときちゃんと血が凝固しやすくするようなものを十分入れておいて、塞栓物質は最終的には溶ける物質の方が子宮へのダメージは抑えられます。
産科的判断のできる産婦人科医とIVRの適否が判断できるIVR医が協力しなければなかなかうまくいかないときもあります。次の妊娠につなげるためにも、産婦人科で対応かIVRが対応か、お互い粘り過ぎず、限界を見極めて治療の役割交代時期を見定めることが大事です。
山門;粘りすぎないというのは大事な視点ですね。大量に出血して大変なときは速やかにご連絡いただきたいですね。そうすれば少しでも早く対応できるようになります。

――産科危機的出血では、両科の先生方が密に連携して患者さんのために対応されているのですね。
山門:ただ全国的にそれができているかというと、そうではないと思います。IVR医が少ないことが一番の問題です。ここは改善の余地が十分あります。日本IVR学会のホームページでは産科危機的出血に対応可能な病院を掲載していて、そこでIVR治療ができるようにしています。
木村:産科危機的出血のような出来事は人口に比例して起こるため、人口が少ないところにはIVRの先生が少なくなりがちです。非常に人口が少ないところにもIVRの先生が必ずいなければいけない、としてしまうと、その先生のお力が生かせない可能性があります。もちろん県内に1人もいないというのは絶対に良くないのですが、貴重な医療資源をどう配置するかは戦略的に考えなければいけないと思います。
――二つ目のテーマは「子宮筋腫のUAE(子宮動脈塞栓術)」についてです。子宮筋腫は女性の4人に1人がなると言われている非常に身近な病気です。日本では子宮筋腫に対するUAEが保険適用になりましたが、まだあまり行われていないそうですね。
木村:子宮筋腫に対する治療で一番多く行われているのは、実は経過観察です。治療としては何もしないのですが、筋腫が大きくなって困ることのないように定期的な通院を提案しています。私は「主訴が明らかになっていない患者さんに治療はしてはいけない」と常々言っています。子宮筋腫はまさに主訴がないことが多い病気ですので触らないことが大前提になります。
UAEはこれから妊娠を希望している方に対しては、安全性が確立しているとはまだいえません。そのため妊娠を希望している方の場合は、例えば症状が強いとか、明らかに筋腫が妊娠を邪魔しているという場合には手術で子宮筋腫だけをとるのが良いでしょう。
一方で妊娠出産は考えていない方や、症状が強く出ていてある程度年齢が高い方は手術で子宮自体を取ることも可能です。そのような方には子宮を取ることと同列としてUAEというのは良い選択肢だと思います。患者さんの中にはUAEをすると筋腫が消えてなくなると思っている方もいるようですが、そうではありません。重さにしたら平均して半分程度になります。少し想像しにくいと思うので、私は次のように患者さんに説明しています。10センチ四方のサイコロに水を入れると1キログラムになります。それを半分の500グラムにするためには、サイコロは5センチではなく8センチにするのです。つまり筋腫はそんなに小さくはなりません。それでも症状の改善率や患者さんの満足度は9割を超えています。もちろんUAEは合併症の可能性はゼロではありませんが、子宮筋腫の非常に大事な治療法の一つであり、満足度も高い治療です。その事実を知ってもらったうえで、どうするかは患者さんのチョイスです。
ただ子宮筋腫の中には、報告によって違いますが、数百回に1回ほど悪性の子宮肉腫があります。ほとんどはMRIを撮ったときに判明します。閉経が近くなってくると、急に肉腫が大きくなる方がいるため注意が必要で、その時はMRIを撮って慎重に治療方針を考えます。
子宮筋腫は基本的に良性の病気で、頻度は4割と言われていますが、本当に細かく調べれば7−8割あるとも言われています。ただ全員が医療介入しなければいけないわけではありません。良性の病期であるからこそ治療の選択肢は多い方が良い。いろいろな治療を知ったうえで、患者さんが治療を選ぶような時代になってきているのです。
山門:基本的にUAEは産婦人科の先生を通してIVR医に話があがってきます。木村先生がおっしゃったように、症状がない場合にはまずUAEはしません。
以前、三重大学で勤務していたとき、倫理委員会で子宮筋腫なら子宮を取ればいいというご意見があったったのですが、女性の看護師長がとても反対されたのです。そのとき、女性にとって子宮の手術はとても抵抗があることなのだと実感しましたね。
私が患者さんに説明するときには、木村先生がおっしゃったように、症状は90%ぐらいなくなりますが、筋腫がすべてなくなるわけではないこと、いろんな合併症が起こる可能性があることを説明します。また妊娠を希望されている方には、妊孕性は確立されていないこともお伝えします。ただ科学に基づいたデータを提示して説明していることもあり、私が担当した中でUAEを選択しなかった方は一人もいませんでした。
最近は、インターネットで調べてこられる患者さんが増えています。自分で情報を取れるようになったことは、患者さんの選択権という意味では悪いことではないと思います。ただその情報の中には間違った情報が混じっていますので、正確な科学に基づいたデータを患者さんに提供することが私たちの仕事の一つだと思います。

――UAEはまだあまり知られておらず、これを手がけるIVR医も少ないと伺っています。
山門:やはりマンパワーが不足していますし、UAE治療の認知不足もあると思います。以前、産婦人科の先生を対象にアンケートをとったのですが、「UAEのことは知っているけれど、よくわからない」「UAEを患者さんに全く説明していない」という回答が多くて驚きました。保険適用の対象となったことを知らない方も多いですね。UAEをする場合、基本的に産婦人科医の先生からのご紹介になるため、学会同士で連携して、UAEという選択肢があることを産婦人科の先生にもお知らせをしていきたいと思います。
――認知拡大という点では、UAEに関する教科書も必要になってくるのではないでしょうか。
山門:そうですね、今『IVRマニュアル』という本を執筆していて、UAEについても取り上げています。なるべくIVR医がUAEを受けた患者さんをIVR病棟で診られるようになればいいのですが、IVR病棟がない施設も多いので、IVR医が産婦人科医と一緒に患者さんを診ていけるような体制が構築されていければいいなと思っています。
――メーカーからの支援も非常に重要になってくると思います。昨年、塞栓物質であるエンボスフィアの販売会社が日本化薬からメリットメディカル・ジャパンに変わりました。日本化薬は長年にわたって学会でのセッションや多くの教育資材を提供していただきましたが、この点についてはどうお考えですか。
山門:メーカーとタイアップしてやっていくことは非常に大事だと思います。例えばアメリカではメーカーといっしょにやることが多いですからね。Win-Winとなれるように、関係を大事にしていきたいと思います。
――子宮筋腫にはいろんな治療の選択肢があるということですが、ほかにはどういった治療法があるのでしょうか。
木村:子宮筋腫は女性ホルモンが少なければある程度小さくなるという性質があるため、脳のホルモンの司令塔である脳下垂体の作用を変えて、女性ホルモンの分泌を抑えるという治療法があります。今まで注射でしかできなかったのですが、それが飲み薬でできるようになりました。ただし女性ホルモンは長く分泌を抑えると閉経の状態を長引かせることにもなるので、投与期間は原則半年までという縛りがあります。月経の問題だけであれば、避妊リングを入れて月経量を減らすというアプローチもあります。避妊リングは5年間持つため、閉経まで3、4年の方であればそれも考慮できます。オプションがたくさんあるので、患者さんには自分にとって何が一番嫌で、何が一番いいことなのかを考えて決めてもらうのが良いと思います。
――最後のテーマは「婦人科悪性腫瘍」についてです。婦人科の悪性腫瘍といえば子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなどがありますが、中でも子宮頸がんはワクチン接種の積極的勧奨が再開されました。木村先生はどのように捉えていますか。
木村:子宮頸がんワクチンをめぐってはいろんな報道があり、一時期、日本人のワクチン接種対象年齢の子たちの7−8割が接種していたのですが、ワクチン接種後の症状をめぐる報道が出た後はほぼゼロになってしまいました。実は私はあの報道がでたとき、ちょうど国際産婦人科連合という各国の産婦人科学会が集まる連合体の理事会に出席していたのですが、「こんな話聞いたことあるか」と聞いてまわったところ「そんな話聞いたことない」「日本ではそんなことが問題になっているのか」とみんな口を揃えて言っていましたね。その時これは大変なことになったと思いました。
ワクチン接種の時期は思春期ということもあり調子が悪くなる方はいるのですが、それは接種しない人でも起り得る事象です。それをいろんな方面で訴えてきたのですが、さまざまな考えの方がいらっしゃることもあり、再開までかなりの時間がかかってしまいました。
私の大学の教室でこの件を熱心に研究しているグループがあるのですが、日本ではワクチン接種が始まりその年齢の人だけ子宮頸がんの発生数がぐんと下がり、接種の中断があったのでまたぐっと上がるだろうということでした。他の国ではワクチン接種が継続されているので子宮頸がんの発生数が一気に下がることしか観測できないので、彼らには、その日本の特殊な状況の事実をデータとして絶対に残さなければならないという話はしました。
――子宮頸がんは検診で対応することはできないのでしょうか。
木村:もちろん子宮頸がん検診は非常に有効でぜひ受けていただきたいのですが、浸潤がんは検診では引っかからないことがあるのです。私たちのところで浸潤がんとして手術をした子宮頸がん患者約80人のうち、約2割の方が過去2年以内にがん検診を受けていました。浸潤がんだと表面が壊死してしまうため、そこの細胞をとっても検診ではでてこないのです。ただもっと早期のがんは非常に高い確率で検出できます。「検診で大丈夫だったから私は病気じゃない」という人もいますが、それは一番まずい。検診でも見つからないがんもあるのだということは、理解しておいてほしいなと思います。
ワクチン接種で難しい状態になった患者さんの報道もありましたが、小児の専門家からすると、ワクチン接種が始まる前からそういう状況はよく起きていたそうです。例えば体育で骨折をしたとか、ケガをしたとか、そういったことがきっかけで、特に思春期のお子さんでは見られる状態であるとのことでした。ですので、たまたまワクチンの痛みで起きてしまったのだろう、という解釈です。COVID‑19ワクチンと同様、注射が結構痛いのですが役に立つということを、しっかり説明していかないといけないですね。現状、接種は再開しましたが、中断してしまったものをもう一度受け入れてもらうのは難しく、接種率はまだ10%程度に留まっています。これをどう上げていくかを今考えているところです。
――その他に婦人科悪性腫瘍について最近のトピックはありますか。
木村:抗がん剤など薬が非常に良くなりましたね。がんが再発された方でも、免疫チェックポイント阻害剤が効くケースが結構あります。とはいえ3割バッターです。みんなに効くものではないので、一定の方については、どこかでがんを小さくするという治療から、症状をコントロールするという治療に変えていかなければいけません。そちらに目標を移す方が、より良い生活を過ごすことができます。その時にはIVRのほか、放射線治療が一つの選択肢になります。
患者さんのステージによって対応方法は決まります。例えば子宮頸がんで大量に出血しているときには動脈塞栓術をすると、後で放射線治療が効かなくなってしまいます。放射線治療は酸素が入ってこないとうまく効かないため、動脈を詰めてしまうと酸素が届かなくなってしまうのです。輸血しながらでもともかく放射線を照射するなど、腫瘍の特徴に合わせて考えます。またものすごく状態が悪い場合や、一旦治療しても再発する場合などで対応はその都度違ってきます。先ほどの子宮筋腫に比べると、選択肢の幅は狭まり、医師が適切な治療を判断することになるのでそこは良性疾患との違いですね。
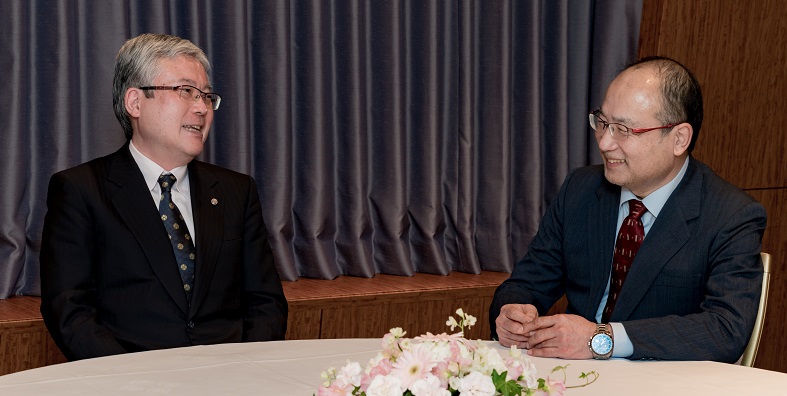
――婦人科悪性腫瘍に対するIVRについても教えてください。
山門:がんが局所再発したときは、がんのところまでカテーテルを入れて、そこに抗がん剤入れることが多いですね。最近は肝臓がん以外のがんにも経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)が保険適用になったので、婦人科腫瘍からの肺転移では、RFAでがんを完全になくすことで長生きされる患者さんもいます。また、肝転移もRFAができます。肺、腎臓、骨、骨盤腫瘍への転移に対して緩和的な意味でもRFAは非常に有効な手段です。ちょうど今、腎臓がんのみ保険適用の凍結治療法についても厚生労働省に保険適応拡大を要望しているところですので、凍結治療で骨転移の治療などもできるようになってくるかと思います。
昔一緒に働いた先生が、20年くらい前に肺の肉腫で骨転移をRFAで焼灼しました。未だに体内に肉腫はあるものの、ゴルフを楽しんでいるそうです。今の時代はがんは人生の敗北ではないので、痛みを取るなどしてQOLを落とさずに生活できるようにしてあげることも、非常に大事だと思いますね。
――日本IVR学会中心にRFA手技のトレーニングコースなども拡充されているそうですね。第75回日本産科婦人科学会学術講演会では日本IVR学会とのジョイントセッションでそのお話をされると聞いています。そもそもジョイントセッションはどういった経緯で始まったのでしょうか。
山門:日本IVR学会の広報渉外委員から日本産科婦人科学会にお声がけし、2020年の日本IVR学会にて初めてのジョイントセッションが始まりました。その時は日本産科婦人科学会から、順天堂大学の牧野先生、大阪大学の澤田先生らに来ていただき、大変盛り上がりましたね。私はその時は観客席で見ていたのですが、本当に産婦人科の先生方は理解のある方ばかりで感銘を受けましたね。非常に有意義でした。
――ジョイントセッションは両学会合わせて7回になるということですが、他にもアンケート企画、筋腫治療の啓発動画等についても、木村教授を始め産婦人科学会と協力して進められたと伺っています
木村:IVRの先生ができることはどんどん増えているので、それをみんなが認識することが大事です。治療にいくつも選択肢があるのは素晴らしいことです。私たちも知識をアップデートし、新しい治療法についても知っていかなければいけないなと思っています。
 山門:私のところには全く治療方法がなくなった患者さんがたくさん来られます。肉腫の肺転移ですと、薬が効かなくなると1年以内に亡くなってしまうことも多い。ですが肉腫を全部RFAで治療すると、5年生存率はぐっと上がってきます。ただ新しい治療のため、IVRがエビデンスを出しながら進めていかなければいけません。日本産科婦人科学会とは関係ができつつあり協力いただけていますが、他の学会にも広めていきたいと思っています。
山門:私のところには全く治療方法がなくなった患者さんがたくさん来られます。肉腫の肺転移ですと、薬が効かなくなると1年以内に亡くなってしまうことも多い。ですが肉腫を全部RFAで治療すると、5年生存率はぐっと上がってきます。ただ新しい治療のため、IVRがエビデンスを出しながら進めていかなければいけません。日本産科婦人科学会とは関係ができつつあり協力いただけていますが、他の学会にも広めていきたいと思っています。
――最後に記事を読まれる日本産科婦人科学会の先生、日本IVR学会の先生にメッセージをお願いします。
木村:全部の施設で連携した高度な治療できるわけではないと思いますが、特に拠点となる施設では両科が良好な関係を結ぶことが非常に大事です。この患者さんにとっては何が一番良いのか、産婦人科は治療の全体を考え、IVRの先生方に相談し、お互いの治療を理解し協力できる体制になることが大事だと思います。今後もIVRの先生方にいろいろご指導ご協力いただければと思っています。
山門:RFAの保険適応拡大は、昨年の日本IVR学会総会と時期が重なったのですが、IVR医はすごく新しい治療に前向きでした。そのようなIVR医から「RFAをやるためには何が必要ですか」と聞かれたときには、「カンファレンス」と答えていました。婦人科疾患の範囲なら婦人科の先生、肉腫なら整形外科の先生、消化器なら消化器内科・外科の先生と、必ずカンファレンスをしてコミュニケーションを取りながら、患者さんにとってためになることは何か話合い進めることが一番大事だと思います。今回木村先生とお話して、やはり各科との連携が一番大事なのだと認識を新たにしました。
――医療は人と人が行うものであり、各科のコミュニケーションがあり、信頼関係があってのことなのだと感じました。今後良好な協力関係が継続、発展していくことを祈っております。本日はお忙しい中ありがとうございました。


更新日: 2023年5月29日


